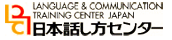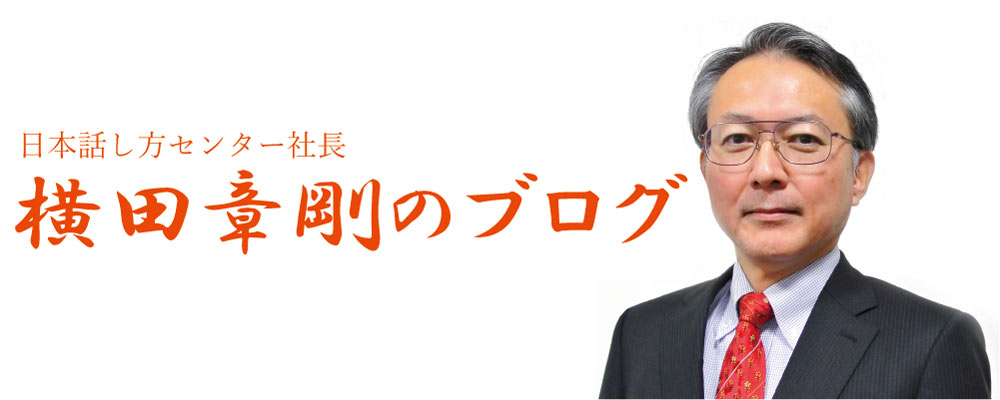2019年11月17日一文を短くする
この土曜日、日曜日の2日間、当センター主催の2日間集中セミナーが開催されました。

会社から社外研修の一環として派遣された方が8割弱、個人で参加された方が2割強でした。
また、参加者は、宮城県、東京都、千葉県、静岡県、大阪府、兵庫県、香川県、高知県と、全国各地から集まっていただきました。
会社参加の方、個人参加の方ともに、とても積極的に講義を聞き、実習に取り組んでいただきました。
その結果、皆さん、終了前のスピーチは、とても聞き応えのある話をされました。
また、終了後、皆さんからは、次のようなコメントをいただきました。
「わかりやすい話をするコツをつかんだ」
「今までの自分の話し方を改善する具体的なやり方がわかった」
「人前で話すことへの苦手意識がなくなった」
「人の話を聴くことがいかに大切か、よくわかった」
さて、2日間集中セミナーでも、ベーシックコースでも、参加者が最初に作成されたスピーチ原稿には、共通した特徴があります。
それは、一文が長い、ということです。
例えば、こんな感じです。
「お客様から電話があり、若手社員が応対していたのですが困っているようなので、私が代わったところ、「あなたのところのサービスは最低だ、一体どんな社員教育をしているんだ」というクレームの電話でした。」
接続詞でつないで、なかなか文章を切らない。「。」がなかなか来ない文章です。
聞き手は、上の例のような長い文章を話されると、頭の中のメモリが一杯になってしまい、話を咀嚼して理解する余裕ができません。
また、この例では、お客様から電話があった → 若手社員が出た → 対応に困っている → 私に代わった → お客様からクレームを受けた、というように、次々と変わる場面を同じ一文で話しています。
こうした話し方では、聞き手は場面が変わっていることについていくことができず、話が途中でわからなくなってしまいます。
わかりやすい話しをするためには、一文を短くすることが必要です。
具体的には、一文の中に、読点(、)が1つ入るくらいにします。
上の例の一文を短くすると、こんな感じになります。
「お客様から電話がありました。
若手社員がその電話に出ました。
しばらく応対していましたが、困っている様子です。
私が代わるよ、と合図を送って電話を代わりました。
すると、「あなたのところの~」というクレームの電話だったのです。」
文章を短くすると、聞き手は、頭の中のメモリにしっかりと一文を記憶し、それを理解してからメモリをクリアできます。
また、一文を区切るときに、自然に文と文の間に「間」ができます。
聞き手は、この「間」があると、その前に話された短い文章を咀嚼する余裕が与えられ、しっかりと理解しながら話を聴くことができます。
場面が変わるところも文章ごとに分けられていますので、聞き手はしっかりとその変化についていくことができます。
2日間集中セミナー、ベーシックコースのどちらも、参加者は最後の成果発表スピーチで、一文が短い話をされます。
一文を短くすることを習慣にするには、少し継続的に努力していただくことが必要ですが、身につければ、絶対に話は分かり易くなります。
ぜひトライしてみてください。